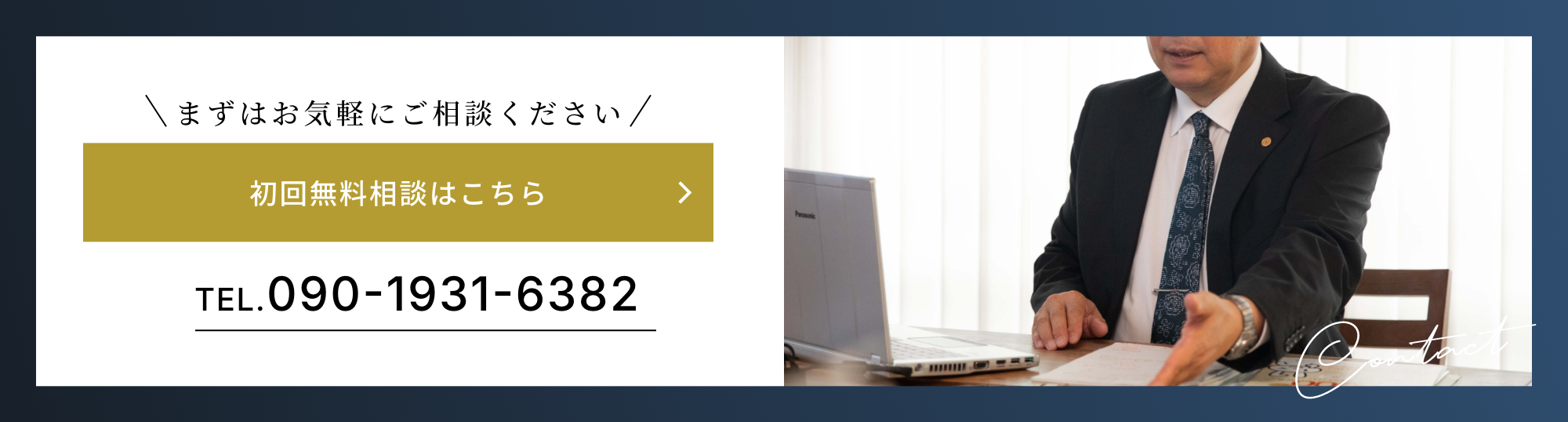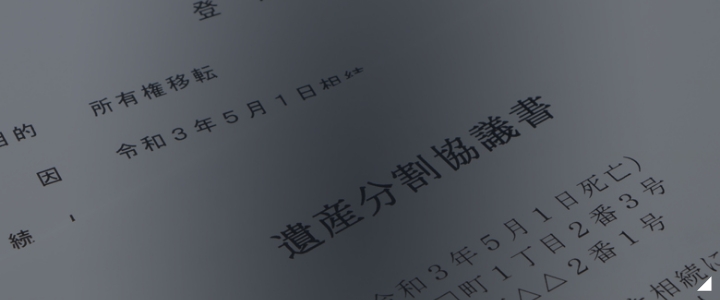ブログ
遺言書の効力と遺留分の注意点 | 西嶋洋行政書士事務所(山形県最上郡)が解説!
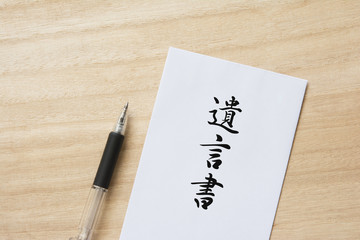
山形県最上郡の皆様へ。
遺言書は、ご自身の想いを形にし、大切な財産を誰にどのように託すかを決める、極めて重要な法的文書です。しかし、作成しただけでは安心できません。遺言書が実際に効力を発揮するためには、法律上の条件を満たすことが不可欠です。
特に注意すべきなのが、「遺留分」という法律上の権利です。遺言書によって誰か1人にすべてを相続させるように書かれていたとしても、他の相続人が遺留分を主張すれば、遺言のとおりにはならないケースがあります。
「せっかく遺言書を作ったのに、思い通りに分けられないの?」
そう疑問に感じた方も多いかもしれません。ですが大丈夫です。遺言書の効力と遺留分の制度を正しく理解し、事前に対策を講じておけば、希望を実現することは十分可能です。
本記事では、山形県最上郡を中心に地域に根差した活動を行う西嶋洋行政書士事務所が、遺言書の効力と遺留分の関係について、分かりやすく・専門的に解説いたします。
目次
遺言書の効力とは何か

遺言書の基本的な効力とは
遺言書の効力とは、法的に有効な遺言書が作成され、被相続人が死亡した後に、その内容に従って財産が分配される法的強制力を意味します。つまり、故人の「最終の意思」を実現する力があるのです。
ただし、どんな内容でも効力を発揮するわけではありません。民法上、以下の条件を満たしている必要があります。
- 法定の方式に従っている(自筆証書、公正証書、秘密証書)
- 遺言者が遺言能力を有している(15歳以上、判断力あり)
- 相続に関する内容が明確である(相続人、財産の範囲、割合)
有効な遺言書があれば、法定相続分に関係なく、故人の意思を尊重した分け方が可能です。たとえば、長年介護を担ってきた娘に多く相続させたい、または特定の相続人には財産を渡したくないといった意向も、効力ある遺言書によって実現できます。
西嶋洋行政書士事務所では、形式面・内容面の両方から「本当に効力を発揮できる遺言書」を目指し、個別の状況に合わせたアドバイスを行っています。特に山形県最上郡では、親族間の誤解や不満が相続を複雑化させることが多く、事前準備の重要性が高い地域といえるでしょう。
有効な遺言書と無効な遺言書の違い
有効な遺言書とされるには、法律で定められた「遺言の方式」に従う必要があります。もっとも一般的なのは自筆証書遺言ですが、書き方を誤ると無効になるリスクがあります。
たとえば、以下は無効となる例です:
- 日付の記載がない、または不明瞭(「○月吉日」など)
- 署名がなかったり、印鑑が押されていない
- 財産の記載が曖昧(「預金」だけで銀行名・口座番号がない等)
こうした形式ミスにより、せっかく書いた遺言書が効力を発揮しない事態に陥ることがあります。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡において、形式確認サービスも行っており、文面のリーガルチェックで有効性を担保します。遺言書を作成した後も、見直し・確認を継続することが大切です。
遺言書の効力が発生するタイミング
遺言書の効力は、遺言者の死亡と同時に発生します。
つまり、元気なうちは効力はありません。生前であればいつでも内容を変更・撤回できますし、他の遺言で上書きすることも可能です。
しかし、死亡後はその内容が法律上の効力を持つため、相続人はその遺言に従って相続手続きを進める義務が生じます。
ただし、次のような例外もあります:
- 遺言執行者が指定されていないと実行に時間がかかる
- 相続人が遺留分を主張し、内容が一部変更される可能性がある
したがって、「死亡=絶対にそのまま実行される」ではないことに注意が必要です。遺言書の効力が確実に反映されるよう、内容の精査と制度への理解が欠かせません。
効力のある遺言書を作成するための注意点
効力のある遺言書を作成するためには、以下の点に注意が必要です。
- 誤解を生まない文面で書くこと(「長男に土地を」ではなく、「○○銀行の定期預金××円を長男○○に相続させる」など)
- 遺留分への配慮を忘れないこと(特定の人に集中しすぎない)
- 遺言執行者を定めておくこと(実行がスムーズになる)
- 定期的に見直し・更新すること
たとえ効力があっても、実行時にトラブルになるような遺言では意味がありません。家族の納得が得られる内容と形式を両立させることが、真に“効力ある遺言書”の条件だといえるでしょう。
山形県最上郡で多い誤解と対策
最上郡地域では、「自分で書いたから大丈夫」「封筒に入れて仏壇にしまっておけば問題ない」といった誤解が多く見られます。しかし、これは非常に危険です。発見されなければ無効と同じですし、家族がその存在を知らなければ、法定相続で進んでしまうこともあります。
また、「すべての財産を妻に相続させる」と書いてあるだけの遺言では、子や親に対する遺留分を侵害している恐れがあり、かえってトラブルのもとになってしまうこともあります。
西嶋洋行政書士事務所では、地域事情に精通した行政書士として、
- 自筆証書と公正証書、どちらが向いているか
- 家族関係の中でトラブルの火種になりうる要素は何か
- 相続財産の整理と記載方法
を個別に分析し、そのご家庭に最も適した遺言書の形をご提案しています。
遺留分と遺言書の関係

遺留分とは何か?その意味と対象
遺留分とは、法律によって保障された最低限の相続権のことを指します。どれだけ自由に財産を誰かに渡したいと考えていても、一定の相続人には必ず一定の割合を残さなければならないという制度です。
具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母など)に対して、本来の法定相続分の1/2の割合が遺留分として認められます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、子が1人いる方が「すべての財産を長男に相続させる」と遺言書に記した場合、他の子は財産を一切もらえないことになります。ですが、法律上はその子にも最低限の財産を請求できる権利(遺留分)が残されているため、その遺言通りにはならない可能性があります。
このように、遺留分は「遺言による自由」と「家族としての最低限の保障」をバランスよく両立させる制度です。つまり、遺言書と遺留分は常にセットで考える必要があるのです。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡での相続案件において、「遺留分を考慮せずに作った遺言書」に起因するトラブルを多く目にしてきました。ご家族全員が納得できる相続を実現するためには、遺言書の作成段階から遺留分への配慮を意識することが不可欠です。
遺言書で遺留分を侵害した場合の影響
遺言書で特定の相続人にすべての財産を譲ると記載し、他の相続人の遺留分を侵害した場合、その遺言書の内容は一部効力を失うことがあります。
これは、遺留分を有する相続人が「遺留分侵害額請求」という手続きを取ることができるためです。つまり、たとえ遺言書で明確に財産の分配を指示していても、遺留分を侵害された側が法的に主張すれば、その部分については修正されるのです。
この請求がされると、実際には「お金で解決」されるケースが多く、受け取った側が一部を返金したり、代償分割で調整したりすることになります。結果として、遺言書の効力が制限されることになるのです。
遺留分侵害額請求の方法と期限
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されたと感じた相続人が、遺言によって財産を多く受け取った相手に対して金銭での支払いを請求する手続きです。
この請求は、相手に対して内容証明郵便などで意思表示を行うことで成立します。実際の請求金額は、遺留分の割合と相続財産の内容に基づいて計算されるため、専門的な知識が必要です。
また、この請求には期限があります。
遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内、または被相続人の死亡から10年以内です。これを過ぎると、遺留分を請求する権利自体が消滅してしまいます。
そのため、遺言書に不満がある相続人がいたとしても、行動を起こさなければそのままになってしまい、後から「気づかなかった」では済まされません。西嶋洋行政書士事務所では、期限の確認と必要な手続きの代行も含めて、遺留分侵害への対応を丁寧に支援しています。
遺言書で遺留分を回避するには?
遺言書を作成する際に、できるだけ遺留分を侵害しないよう工夫することがトラブル回避のカギです。
まず一つの方法として、遺留分に配慮した分配の記載を行うことが挙げられます。たとえば「長男に自宅を相続させるが、次男には遺留分に相当する現金を残す」といった形で、遺言書の中に配慮を明記することで、納得を得やすくなります。
また、遺留分放棄の手続きも選択肢の一つです。これは生前に家庭裁判所の許可を得て行うもので、相続開始前に一定の相続人が遺留分を放棄することができます。ただし、放棄には相続人自身の同意と裁判所の判断が必要なため、事前に十分な説明と合意形成が必要です。
西嶋洋行政書士事務所では、「誰に何を、どのように残すか」を丁寧にヒアリングし、遺留分を侵害しない遺言書の作成をサポートしています。
実務での対応と西嶋洋行政書士事務所の支援
遺留分と遺言書の関係は、机上の理屈だけでは解決できません。実際の相続では、家族の関係性や感情、過去の出来事などが複雑に絡み合います。
たとえば、親と同居していた長男に多く遺産を残す遺言書を作成しても、疎遠だった次男が「納得できない」として遺留分を請求することがあります。このようなケースでは、相続発生後に“争族”が発生しやすく、家族の関係が崩れてしまう可能性があります。
だからこそ、遺言書の作成段階から遺留分への配慮が必要であり、第三者である専門家の関与が極めて重要です。
西嶋洋行政書士事務所では、
- 相続財産と法定相続人の確認
- 遺留分を考慮した遺言書の設計
- 想定される遺留分請求への備え
- ご家族への説明サポート(場合により家族会議も)
といった実務的な支援を行っており、最上郡で「家族全体が納得できる相続」をサポートしています。さらに、遺言書の保管、定期見直し、そして万が一の遺留分請求への対応に至るまで、一貫した伴走支援をご提供しております。
遺言書と遺留分をめぐる実例

実際にあった相談事例と背景
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡においてこれまで多くの相続に関するご相談を承ってきました。その中でも「遺言書があるのにうまく相続が進まない」「遺留分の請求を受けた」といったトラブルが発生するケースは少なくありません。
たとえば、あるご相談者様(80代男性)は、長男夫婦と長年同居していたことから、「すべての財産を長男に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していました。しかし、相続が発生した際、遠方に住む次男がその内容に納得できず、「自分には何も残らないのか」として遺留分侵害額の請求を行いました。
ご本人としては「長男に全て任せたい」という思いだったのですが、遺留分の知識がなく、結果的にトラブルの引き金となってしまったのです。
このように、どれだけ本人の意思が明確であっても、遺言書の内容と遺留分制度がぶつかると紛争につながる恐れがあります。相続人全員が納得していない限り、法的な対抗手段が取られる可能性を常に考慮する必要があります。
私たちはその経験から、遺言書作成時に「この内容で誰かが不満に思う可能性はないか?」「遺留分を侵害していないか?」をシミュレーションすることが極めて重要であると強く感じています。
事例①:相続トラブルに発展したケース
最上郡在住のA様(故人)は、生前に遺言書を自筆で作成し、「妻に全財産を相続させる」と記載していました。しかし、相続開始後にその内容を知った長男が「父が一方的に決めた」として遺留分侵害額請求を起こしたのです。
このケースでは、財産の多くが自宅不動産であったため、妻が相続した家を売らなければならない可能性も生じました。遺言の効力はあったものの、遺留分の権利とぶつかってしまい、家族全体の生活に影響を及ぼしました。
事前に家族間で話し合いをしておけば防げた可能性が高いだけに、ご本人も遺族も非常に悔やまれる結果となりました。
事例②:遺言書と遺留分を両立した成功例
一方で、最上郡のB様(70代女性)は、「自宅は長男に残したいが、次男にも不満が出ないようにしたい」と考え、西嶋洋行政書士事務所にご相談くださいました。
私たちは、
- 不動産を長男へ
- 同等程度の預金を次男へ
- 両者に説明文を添えた遺言書
というバランス型の内容をご提案。さらに、家庭裁判所で次男に遺留分放棄の同意を得る手続きも支援しました。
結果として、相続開始後もスムーズに手続きが進み、家族関係も良好なまま保たれました。遺言書と遺留分は対立するものではなく、工夫と配慮によって共存できるのです。
事例③:遺言書の文言ミスによる無効事例
C様のケースでは、自筆証書遺言に「次男に“土地”を相続させる」とだけ記載していました。しかし、土地の所在地や登記番号が明記されておらず、どの土地かを特定できないために無効となりました。
さらに、その内容が遺留分の配慮もないものであったため、長男が遺留分を請求し、結果的に財産の大部分が法定相続通りに分配されました。
このような事例では、「せっかく遺言書を書いたのに、実際には効力を発揮しなかった」という残念な結果になります。法律のルールに沿った明確な文言と遺留分の理解が不可欠です。
地域事情を踏まえた事前対策の重要性
山形県最上郡の地域特性として、農地・山林・自宅などの不動産が中心の財産構成であることが多く、また兄弟姉妹が近隣に住んでいることも多いため、相続人同士の関係性が密接である傾向があります。
そのため、財産を一部の人に集中させる遺言書を作成した場合、他の相続人が感情的に反発しやすく、遺留分を主張するケースが多く見られます。
特に、
- 長男だけが親の介護を担っていた
- 他の兄弟が経済的に困窮している
- 遺言内容に対する説明が一切なかった
などの事情がある場合、遺留分をめぐって家庭内の争いが深刻化するリスクが高まります。
西嶋洋行政書士事務所では、そうした背景を踏まえ、
- 遺言書の説明文(付言事項)の活用
- 財産の分割方法に対する工夫
- 生前の家族会議サポート
などを通じて、地域性に合った相続対策をご提案しています。
単に「法律的に有効」な遺言書を作るのではなく、「家族が納得し、争わない」ことをゴールに据えた支援。それが、当事務所が最上郡の皆様に提供している価値です。
有効な遺言書を作成する流れと注意点

遺言書作成の基本的な流れ
遺言書を作成する際は、ただ「思いを書き残せばよい」というわけではありません。法律上の要件を満たし、内容が明確であり、将来にわたって効力を持つ形で作成する必要があります。以下に、遺言書作成の基本的な流れをご紹介します。
まず最初に行うべきことは、財産の把握と整理です。不動産、預貯金、株式、車、貴金属など、すべての資産をリスト化することが大切です。西嶋洋行政書士事務所では、最上郡のお客様の生活背景に合わせて、農地や山林、地域特有の共有財産まで丁寧に確認いたします。
次に、相続人の確認を行います。法定相続人が誰なのか、前妻の子がいるか、認知した子がいるかなど、家族関係の確認が極めて重要です。この段階で見落としがあると、後々のトラブルの原因になります。
その後、遺言の内容を設計します。誰にどの財産をどのように渡すのか、遺留分の配慮を含めて構成を考えることが求められます。
遺言書の方式は主に以下の3つです:
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
多くの場合、公正証書遺言を推奨しています。公証人が関与し、形式ミスが起こらず、紛失や改ざんの恐れがないためです。
作成後は、内容が確実に発見・実行されるように、保管場所や信頼できる人への告知も重要です。
この一連の流れを専門家とともに行うことで、形式・内容・実行性を兼ね備えた“本当に使える遺言書”を作成することが可能になります。
自筆証書遺言作成時の注意点
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる一方で、形式不備による無効のリスクが非常に高い遺言方式です。特に多いミスは以下のようなものです:
- 日付が「○月吉日」などと曖昧に書かれている
- 本人の署名がフルネームでない
- 押印がない、または認印で不明瞭
- 財産の記載があいまい(例:「預金を子に」)
こうしたミスが一つでもあると、遺言書の効力が否定される可能性があります。最上郡では自筆証書を自宅で保管していたが見つからなかった、というケースもよくあります。
西嶋洋行政書士事務所では、法務局の保管制度の活用、または記載内容のリーガルチェックを通じて、自筆証書遺言の安全性と有効性をサポートしています。
公正証書遺言作成時の注意点
公正証書遺言は、最も信頼性が高い遺言方式です。公証人が法律に基づいて作成し、内容の確認もされるため、形式不備の心配がほぼありません。
ただし、公正証書遺言にも注意点があります。
- 事前に財産や相続人の情報を整理する必要がある
- 証人2名の同席が必要(親族以外)
- 公証役場に出向く必要がある(出張可)
また、公正証書遺言であっても、遺留分のことを考慮していなければ、効力は制限される可能性があります。そのため、法的に正しい内容であるだけでなく、相続人全体にとって“納得できる内容”であることが重要です。
最上郡にお住まいの方で、高齢や身体的理由により出向が難しい場合には、当事務所が訪問相談と公証人との連携をサポートいたします。
財産の分け方で注意すべきポイント
財産の分け方を考える際、最も大切なのは「誰が何を望んでいるかを理解すること」です。
たとえば、「不動産は長男に、預貯金は次男に」というように、価値が異なる財産を公平に分けるには細かな配慮が必要です。不動産は売却できない場合もあるため、流動性のある資産でバランスを取る必要があります。
また、特定の相続人に多く残したい場合には、寄与分や特別受益の考慮、または生前贈与との調整も検討する必要があります。
西嶋洋行政書士事務所では、財産目録の作成から、評価方法、分配案の提示まで丁寧に対応し、トラブルのない分け方の実現をお手伝いしています。
西嶋洋行政書士事務所によるサポートの特徴
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡を中心とした地域密着型の相続サポートを提供しております。
遺言書の作成はもちろん、遺言書の効力や遺留分を正しく理解し、それを前提とした実効性の高い文書作成を重視しています。
当事務所のサポートには、次のような特徴があります:
- 無料相談を毎月22日に実施し、誰でも気軽にご相談可能
- 財産や相続人の状況を基にしたオーダーメイドの遺言書作成支援
- 公証役場との連携、公正証書遺言の手続きもすべて代行可能
- 遺言書の保管、更新、遺言執行のアフターサポートも充実
- 相続トラブルを予防するための遺留分調整や家族向け説明書の添付
「何をどうすればよいかわからない」「家族に迷惑をかけたくない」
そんな思いを抱える方にこそ、私たちが寄り添いながら、安心の終活をご提案いたします。
地域に根ざした当事務所だからこそできる、一人ひとりに合わせた温かい相続対策を、ぜひご活用ください。
無料相談のご案内と当事務所の取り組み

毎月開催のオンライン無料相談とは
西嶋洋行政書士事務所では、「相続のことが心配だけれど、誰に相談してよいかわからない」「遺言書を作りたいけれど、費用や方法が不安」といったお声にお応えし、毎月22日に無料相談を実施しています。
この無料相談は、山形県最上郡を中心に、地域の皆さまが気軽にご参加いただけるよう、オンライン形式(Zoom/電話)でも対応しています。ご高齢の方、外出が難しい方、遠方にお住まいのご家族との同時相談も可能です。
ご相談内容の一例は次の通りです:
- 遺言書の正しい書き方を知りたい
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?
- 遺言の効力は本当にあるの?
- 遺留分は考慮しないといけないの?
- すでに書いた遺言書がこのままでよいか見てほしい
ご相談は30〜60分、完全予約制で実施しております。話しにくいことでも、第三者である私たちが丁寧にお伺いし、最善の方法をご一緒に考えます。
相談予約の方法と流れ
無料相談のご予約は非常に簡単です。
お電話、当事務所のホームページ、お問い合わせフォーム、またはメールにて、「無料相談希望」とお伝えいただくだけでご予約が可能です。
日程が合わない場合は、22日以外でも個別に調整可能ですので、ご遠慮なくお申し出ください。
相談当日は、事前に資料(財産一覧、戸籍謄本など)があればより具体的なアドバイスが可能です。もちろん、何も準備がなくても問題ありません。「まず話してみたい」という気持ちがあれば十分です。
無料相談で得られるメリット
無料相談では、ただ話を聞くだけではありません。
西嶋洋行政書士事務所では、実際に相談にお越しいただいた方へ次のようなメリットをご提供しています。
- 相続・遺言に関する初期診断が無料で受けられる
- ご自身の財産や家族構成から考えた最適な遺言書の形を提案
- 遺留分や効力の問題が生じる可能性のある箇所を明確化
- 将来的な相続リスクを予防するためのチェックリストを進呈
一人で悩むよりも、まずは専門家に話してみることで道筋が見えてきます。無料でご自身の状況を「見える化」することができるのは、今後の準備において非常に大きな第一歩となるでしょう。
よくある不安への対応
ご相談者さまからよく聞かれる不安は、「こんなこと聞いてもいいのかな?」「家族に知られずに相談できるの?」というものです。
当事務所では、守秘義務を徹底しており、ご相談の内容がご家族や第三者に知られることは一切ありません。また、相続や遺言は感情が絡む繊細な話題ですので、無理に家族を交えず、まずはご本人だけでのご相談も歓迎しております。
また、「すぐに手続きが必要なのか?」「費用はどのくらい?」といった疑問についても、ご希望に合わせて丁寧にご案内し、強引な提案は一切いたしません。
ご家族との関係性を大切にした提案
遺言書や相続対策は、単なる法律文書の作成ではありません。そこにはご家族への思いや、過去の出来事、現在の関係性がすべて関わってきます。
たとえば、「親の介護をしてきた子に多く残したい」「疎遠な相続人にできれば財産を渡したくない」など、それぞれに背景があります。私たちは、それらを「わがまま」ではなく、人生の選択と尊重しながらサポートします。
また、最上郡のような地域社会では、相続人同士が近くに住んでいたり、親戚付き合いが密であるため、相続をきっかけに家族関係が壊れてしまうことを何よりも避けたいというご相談が非常に多いです。
そのため当事務所では、
- 家族会議の進め方アドバイス
- 付言事項による「思いの伝わる遺言書」の作成
- 円満相続に向けた第三者調整
など、家族がつながる相続をサポートする提案を重視しています。
遺言書の効力を最大限に活かし、遺留分に配慮しつつも、ご自身の希望を形にする。
それが、私たち西嶋洋行政書士事務所の使命です。
(Q&A)よくあるご質問にお答えします

Q1. 遺言書はどのような種類がありますか?
A1. 主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆は費用がかかりませんが形式不備が多く、公正証書は専門家と作成するため効力が確実で実行性が高いのが特徴です。
Q2. 遺言書があれば、どんな内容でも実現できますか?
A2. 遺言書の内容は原則として尊重されますが、遺留分を侵害する内容の場合、請求によって一部修正されることがあります。そのため、自由な内容にするには遺留分への理解が必要です。
Q3. 遺留分は誰にどのくらいあるのですか?
A3. 遺留分は、配偶者・子・直系尊属(父母など)に認められます。兄弟姉妹にはありません。割合は通常、法定相続分の1/2です。詳しくは家族構成により異なるため、当事務所で個別にご説明します。
Q4. すでに遺言書を書いているのですが、有効か不安です。
A4. ご自身で作成された場合、法律上の形式を満たしていない可能性があるため、ぜひ一度専門家の確認を受けてください。当事務所では無料でチェックを行っています。
Q5. 遺言書を家族に知られたくないのですが、相談できますか?
A5. もちろん可能です。西嶋洋行政書士事務所では秘密厳守を徹底しており、個別での対応に加え、匿名でのご相談も対応可能です。安心してお話しいただけます。
Q6. 遺留分の請求には期限がありますか?
A6. はい、あります。相続があったことと、遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければなりません。
Q7. 無料相談ではどこまで対応してもらえますか?
A7. 無料相談では、現状の整理・遺言書の形式や内容のアドバイス・遺留分や効力に関する解説まで対応可能です。必要に応じて、具体的な手続きの流れもご案内します。
まとめ

遺言書は、あなたの意思を形にする最後のメッセージです。
しかしそのメッセージが、正しく伝わらず、実現されなければ意味がありません。
本記事で解説してきたように、遺言書には法律的な効力を発揮するための条件があり、また遺留分という制度によって内容が制限される可能性もあるため、単に「書いただけ」で安心してはいけません。
特に山形県最上郡では、家族関係が密接で、農地や山林など特殊な財産が多く、相続が複雑になりがちです。だからこそ、地域の事情に精通した専門家のサポートが重要です。
西嶋洋行政書士事務所では、
- 遺言書の作成・見直し
- 遺言の効力確認
- 遺留分への配慮
- 相続トラブルの予防
- 家族の未来を見据えた終活支援
を通じて、安心できる相続と納得できる遺言の実現をお手伝いしています。
「何から始めればいいか分からない」「自分の遺言に問題がないか不安」
そんな方は、まずはお気軽に毎月22日の無料相談をご利用ください。
私たちは、“わからない”を“わかって安心”に変えるお手伝いをいたします。
-

遺産分割と生前贈与の重要性について
遺産分割と生前贈与は、家族の財産管理において非常に重要なテーマです。これらの手続きは、単に財産をどのように分配するかだけでなく、家族間の関係を維持し、円満な相続を実現するための重要な要素です。適切な計画と手続きを行うこと…
-

遺産分割における不動産の評価方法と重要性:西嶋洋行政書士事務…
遺産分割において、不動産の評価はしばしば最も困難な課題の一つとなります。不動産は、単に物理的な資産としての価値だけでなく、その土地や建物が持つ歴史的、感情的な価値も含まれるため、相続人それぞれが異なる見解や希望を持つこと…
-

遺産分割のやり直しと時効について:西嶋洋行政書士事務所が解説
遺産分割は、遺産をどのように相続人に分けるかを決定する重要なプロセスです。このプロセスが一度完了した後でも、様々な事情によってやり直しが必要になることがあります。例えば、新たに発見された遺産や、相続人の間での意見の相違、…
アクセス
ACCESS

- 住所
- 〒999-6401
山形県最上郡戸沢村大字古口341番地1
JR陸羽西線「古口駅」より徒歩3分
- Tel
- 090-1931-6382
- FAX
- 0233-72-2662
- 営業時間
- 9:00~12:30
14:00~17:30
- 定休日
- 土日祝日