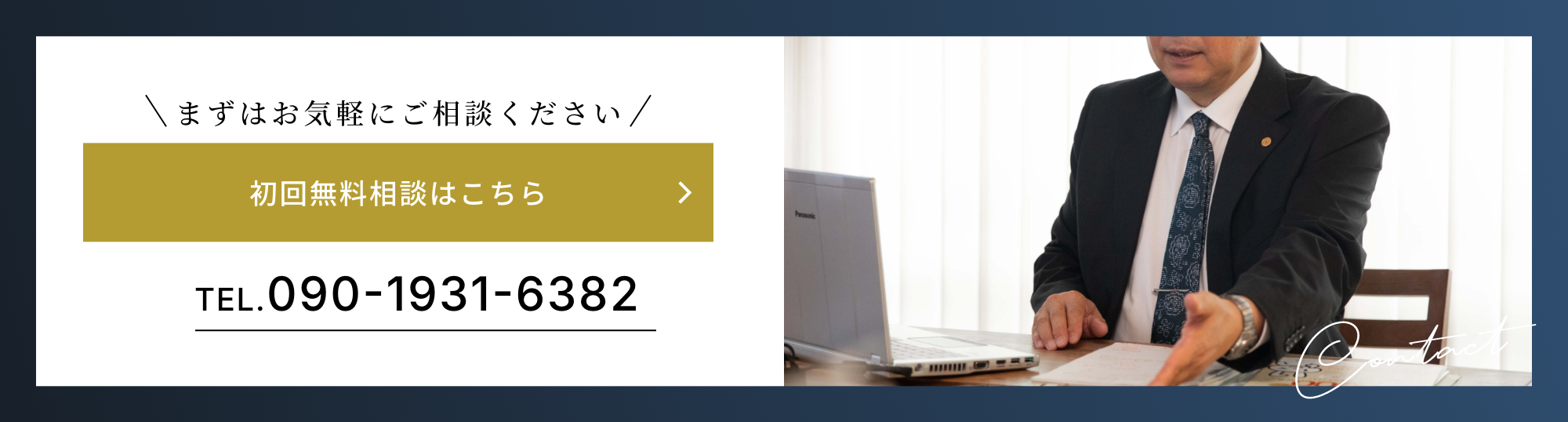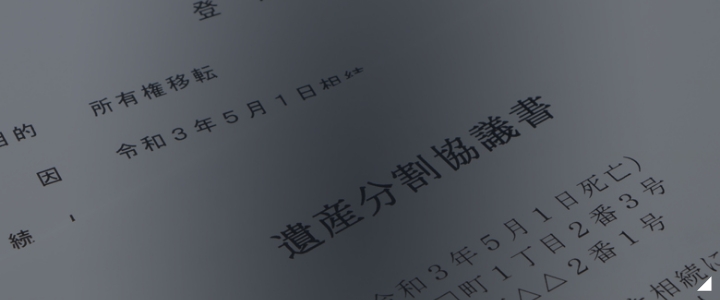ブログ
遺産分割での特別受益とは?|西嶋洋行政書士が徹底解説

「遺産分割 特別受益」という言葉をご覧になり、今この記事を読んでくださっている方の多くは、「相続のときに、生前に多く援助を受けた兄弟がいるけど、それって不公平では?」「住宅資金の援助や結婚費用が“特別受益”にあたるって本当?」などと感じていらっしゃるのではないでしょうか。
特別受益とは、相続人の中で特定の人が生前贈与などにより他の相続人より多くの財産を先に得ていた場合に、それを遺産分割の際に考慮して調整する仕組みです。この制度は、遺産分割における「公平性」を保つために重要な役割を果たしています。
しかし、特別受益が実際にどのように評価されるのか、どこまでが対象となるのか、また、どうやって証明するのかといった点には多くの誤解や混乱が生じやすいのも事実です。感情的な対立に発展することもあり、慎重な対応が求められます。
本記事では、山形県最上郡で行政書士事務所を営む「西嶋洋行政書士事務所」が、特別受益について法律的な基礎から具体的な対処法までをわかりやすく、かつ専門的にご説明いたします。
相続に不安を抱えるご家族が、「知識・理解・納得」できるようになること、そして「西嶋洋行政書士事務所に相談してみようかな」と思っていただけるような内容を目指しています。
山形県最上郡という地域の特性も踏まえながら、実務に即した内容で解説してまいります。どうぞ最後までご覧ください。
特別受益とは何か

特別受益の定義と法的根拠
特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前に特別な利益を受けた場合に、それを相続財産の前渡しとして扱う制度です。これは、民法903条に定められており、遺産分割において「公平性」を保つための仕組みです。
民法第903条1項では、「共同相続人中に被相続人から特別の利益を受けた者があるときは、被相続人はその利益を他の共同相続人に対して遺産の一部として評価し、全体の相続財産に加えて分割すべきである」と規定されています。これはつまり、生前に多くもらっていた相続人の取り分を調整しましょうという考え方です。
たとえば、父親から長男が住宅資金として1,000万円の援助を受けていた場合、父が亡くなった後の相続時に、この1,000万円は「すでに相続したもの」とみなされ、他の兄弟との間で相続分を調整することになります。こうした「持戻し」と呼ばれる仕組みによって、他の相続人とのバランスを取ります。
ただし、すべての贈与が特別受益に該当するわけではありません。親が子に日常的に行う援助(例:生活費や小遣い)や、ごく少額の祝い金などは、特別受益として扱われないことが多いです。
西嶋洋行政書士事務所では、こうした特別受益かどうかの法的判断を、山形県最上郡の実情に合わせて丁寧に行っています。地域の生活慣習や家族の実態を考慮することで、実務に即した助言が可能です。
特別受益に該当する具体例
特別受益に該当する典型的なケースには、以下のようなものがあります。
まずは「結婚に伴う持参金や支度金」。たとえば長女にだけ高額な結婚支援があった場合、これが特別受益にあたるとされることがあります。
次に「住宅取得資金」。長男がマイホームを購入する際に被相続人からまとまった資金援助を受けていた場合、これも特別受益と認定されやすいです。
また「学費」も対象となる場合があります。とくに高額な私立大学・留学・専門学校などにかかった費用が特定の子だけに支払われていた場合は、他の兄弟と差が大きいと評価され、特別受益となることもあります。
ただし、あくまでも相続の公平性という観点からの評価であるため、家庭ごとの事情を丁寧に確認することが大切です。
特別受益の時期と評価方法
特別受益として評価する金額は、原則として贈与を受けた当時の価値で判断されます。ただし、時価が大きく変動する不動産などは、相続時点での評価を用いることもあります。
たとえば、10年前に1,000万円の不動産を取得した場合、現在の価値が2,000万円になっていたとしても、原則は当時の1,000万円を特別受益額として扱います。
このように評価基準には柔軟性が求められるため、相続人間で納得できる説明が非常に重要になります。必要に応じて不動産鑑定士や税理士との連携も検討します。
西嶋洋行政書士事務所では、評価に関する資料収集や、適切な専門家との連携もサポートしています。
特別受益と贈与の違い
贈与は基本的に当事者間の自由な契約であり、受け取った人の自由財産とされます。しかし、相続人間で不公平が生じるような贈与については、特別受益として「相続財産の前渡し」として扱われるのです。
つまり、特別受益は「相続の場面でのみ問題になる贈与」だと言えます。たとえ正式な贈与契約書がなくても、家族内の金銭の動きが証明されれば、特別受益と認定される可能性があります。
この違いを理解しないまま遺産分割協議を進めてしまうと、不公平な分割となってしまい、後々トラブルになることがあります。
山形県最上郡での事例紹介
山形県最上郡では、親から長男が家や土地を相続し、他の兄弟には現金を分けるという形がよく見られます。これは地域の家督制度的な文化に基づいた実務慣行であり、形式的には特別受益が発生している可能性があるものの、家族間で暗黙の了解が成立しているケースもあります。
しかし、近年では他の相続人が県外や都市部に住んでいることも多くなり、「長男がもらいすぎでは?」という不満が表面化する場面も増えています。
ある事例では、長男が農地と住居を相続し、他の兄弟には一切財産が分けられなかったため、次男が特別受益の主張を行い、調停にまで発展したケースがありました。結果として、農地の一部を売却し、他の兄弟に現金で補填することで和解に至りました。
こうした地域性を踏まえた調整には、山形県最上郡の家族事情や不動産事情を熟知した専門家の介入が不可欠です。
西嶋洋行政書士事務所では、地域事情に詳しい立場を活かして、公平な分割と家族関係の維持の両立を目指した支援を行っています。
特別受益の持戻しとは

持戻し計算の仕組み
「持戻し」とは、特別受益を受けた相続人がすでに取得した財産を相続財産に一度“戻す”ことで、相続人間の公平を図る仕組みです。民法903条に定められており、相続財産の総額を算定する際に、被相続人が生前に贈与した特別受益分を加算してから、各相続人の取り分を決定します。
たとえば、相続財産が2,000万円あり、長男が生前に住宅資金として1,000万円を受け取っていたとします。この場合、法的には遺産総額を3,000万円とみなし、そこから法定相続分を計算することになります。
相続人が長男と次男の2人だけなら、それぞれの法定相続分は1,500万円。長男はすでに1,000万円を受け取っているため、残りの500万円のみを新たに相続できるという計算になります。一方、次男は現金で1,500万円を受け取ることになります。
このようにして、特別受益によって相続に不公平が生じないよう調整を行うのが「持戻し」の基本的な考え方です。遺産分割にあたっては、この持戻しの有無や金額について相続人全員で正確に把握し、合意を形成することが重要です。
西嶋洋行政書士事務所では、持戻し計算に必要な財産調査や評価、相続人への説明まで、一貫したサポートを提供しております。
計算方法と分割割合への影響
持戻しによって加算された遺産額に基づいて、各相続人の相続割合が再調整されるため、分割のバランスが大きく変わることがあります。
特別受益がなければ1/2ずつ相続できるケースでも、過去に高額な援助を受けた相続人の取り分は大きく減る可能性があるのです。
この計算は単純な数学ではありますが、感情面で納得できないということがしばしばあります。そのため、数字だけでなく、その背景や経緯を丁寧に共有し、相続人間の理解を得ることが不可欠です。
遺言による持戻し免除
民法では、被相続人が「特別受益の持戻しをしない」と遺言に明記することで、持戻しの対象から除外することも可能とされています。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。
たとえば、「長男には住宅資金を援助したが、それは持戻し不要とする」と遺言で記しておけば、他の相続人はその援助を特別受益として主張できなくなります。つまり、被相続人の意思を尊重して遺産分割を進めるという考え方です。
ただし、この意思表示が曖昧であるとトラブルの原因となるため、遺言書の作成には専門家のサポートが望ましいです。
特別受益と遺留分との関係
持戻しと同様に注意が必要なのが、「遺留分」との関係です。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分であり、特別受益によってこの権利が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能です。
たとえば、長女に大半の財産が生前贈与され、他の兄弟に相続がほとんどなかった場合、遺留分が侵害されている可能性があるため、法律上、他の相続人が差額の請求を行うことができます。
つまり、特別受益と遺留分は密接に関係しており、どちらも無視して分割を進めると法的なリスクが生じることになります。
西嶋洋行政書士事務所の対応
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡の地域事情に根ざした形で、特別受益と持戻しに関するサポートを総合的に提供しています。
まず、財産の調査と聞き取りを通じて、「これは特別受益にあたるのか?」「評価額はいくらか?」といった点を法的観点から丁寧に検討します。次に、持戻しが必要な場合には、分かりやすい図や資料を使って、相続人全員が納得できるよう説明いたします。
さらに、遺産分割協議書への持戻し反映、税理士や司法書士との連携による相続税・登記対応、必要に応じて遺言書の作成アドバイスまで、包括的な支援体制を整えています。
実際に、「住宅資金として受け取ったお金が特別受益かどうか分からず、親族内で揉めていたが、丁寧な説明で皆が納得してスムーズに話がまとまった」という声も多く寄せられています。
西嶋洋行政書士事務所の特徴は、単なる法的助言だけでなく、家族間の感情にも配慮した調整力です。最上郡という地域ならではの相続事情に通じているからこそ、円満で納得のいく相続の実現が可能になります。
特別受益をめぐるトラブル

特別受益の有無に関する争い
遺産分割において最も多く見られる争いの一つが、「特別受益があったのか、なかったのか」に関する対立です。これは金銭の受け渡しが過去の出来事であることが多く、記録や証拠が乏しい場合に主張がぶつかり合いやすいからです。
たとえば、長男が「住宅資金は借りたものであり、贈与ではない」と主張し、次男が「それは明らかに援助だった」と主張すれば、お互いの言い分が平行線をたどることになります。また、「援助の記憶はあるが、金額ははっきり覚えていない」という場合も少なくありません。
このような状況では、過去の通帳記録、振込履歴、贈与契約書、被相続人のメモや日記などが重要な証拠となります。相続人が複数いる場合には、それぞれの記憶や認識が異なるため、事実関係を一つ一つ丁寧に整理する作業が不可欠です。
西嶋洋行政書士事務所では、こうした争いに直面した際に、証拠の収集・整理から法的見解の説明、話し合いの調整まで一貫した対応を行っています。特に山形県最上郡では、親族同士の関係が密接である反面、長年の感情が絡むことも多く、法的知識だけでなく「家族としての配慮」も必要になる場面が多々あります。
冷静な第三者の立場から公平に物事を見て、丁寧に事実関係を確認しながら対応を進めることが、解決への第一歩となります。
感情的対立を避けるには
特別受益に関する話し合いは、非常にデリケートです。なぜなら、お金だけでなく「親からの愛情」や「家族内の優遇・不遇」といった感情が関係してくるからです。
たとえば、「なぜあの人だけ学費を全額出してもらえたのか?」「兄ばかりが優遇されてきた」という不満が、相続の場で爆発することも少なくありません。
こうした感情的対立を避けるためには、事実に基づいた丁寧な説明と、冷静に話し合うための場づくりが必要です。家族だけでの話し合いでは感情的になりやすいため、中立的な専門家を交えることが有効な手段となります。
立証責任と証拠の取り扱い
特別受益があったことを主張する側が、その事実を証明する責任(立証責任)を負います。つまり、「兄は過去に住宅資金を受け取っていた」と主張する場合には、それを裏付ける証拠を提示しなければなりません。
証拠となるものは、振込明細、契約書、メール・LINEの履歴、メモ、家族の証言など様々ですが、時間が経っているほど発見が難しくなります。
西嶋洋行政書士事務所では、相続発生前・発生後問わず、証拠の有無や評価方法についての助言を行い、必要であれば書類の取り寄せや分析もサポートしています。
裁判になった場合の流れ
特別受益に関する主張が折り合わず、協議や調停でも解決しない場合には、家庭裁判所での審判または訴訟に発展する可能性があります。
審判では、各相続人が証拠を提出し、裁判官が事実関係を認定した上で、相続分や持戻しの有無について法的判断が下されます。
訴訟になれば、さらに手続きが複雑になり、時間も費用もかかるうえ、家族関係に決定的な亀裂が入ることもあります。
だからこそ、できる限り裁判に進む前に、専門家を交えた早期の合意形成が望ましいのです。
専門家を交えた円滑な解決
特別受益に関する争いは、法律だけでなく人間関係や感情が複雑に絡み合うため、第三者の視点で冷静に状況を整理できる専門家の存在が不可欠です。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡という地元に根差した立場から、親族の関係性や地域文化も踏まえた円満な話し合いの進行を得意としています。
たとえば、相続人が全員集まることが難しい場合は、個別の聞き取りや書面による意思確認を行い、相互の誤解や不信感を和らげる調整を行います。また、必要に応じて弁護士や税理士とも連携し、法的・税務的な側面からも支援を行います。
「裁判にしたくない」「家族と関係を壊したくない」「でも納得のいく相続をしたい」——そんな思いを持つ方に対して、専門的知識と豊富な経験に基づいた実務的な助言と安心できる調整サポートを提供しています。
特別受益に関して悩んでいる、もしくはこれから問題が起きそうだと感じている方は、ぜひ一度、西嶋洋行政書士事務所にご相談ください。早めの相談が、家族を守る第一歩です。
特別受益と遺産分割協議

協議の進め方と注意点
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の財産をどのように分けるかを話し合う手続きです。この協議において、特別受益があったかどうかは極めて重要な論点になります。
まず、協議を始める前にすべきことは、相続人全員の確認と相続財産の把握です。これは戸籍の収集と財産目録の作成という形で行います。そのうえで、特定の相続人が生前に受け取っていた援助や贈与が「特別受益」に該当するかどうかを話し合い、持戻しの計算を踏まえて、実際の分割割合を調整する必要があります。
ここで問題になるのが、相続人の認識の違いです。「あれは援助ではなく借金だった」「長男ばかり優遇されていた」など、感情と記憶に基づく主張がぶつかり合うことが多々あります。それにより、協議が頓挫するケースも少なくありません。
このようなときこそ、第三者の視点を持った専門家の関与が効果的です。西嶋洋行政書士事務所では、相続人間の公平性と法的妥当性を踏まえて、具体的な分割案や説明資料の作成、協議の進行サポートまで幅広く対応しています。
また、遺産分割協議書を作成する際には、特別受益の内容や金額を記載する必要があるかどうかも、状況に応じて判断されます。あえて記載せずに済ませることもありますが、それが後々の誤解や争いにつながらないよう、慎重な判断が求められます。
遺産分割協議は、単なる話し合いではなく、法的効力を持つ結果を生む重大な手続きです。だからこそ、特別受益という繊細な論点を扱う際には、正確な知識と冷静な進行が欠かせません。
相続人間の認識のずれ
特別受益をめぐる話し合いでは、相続人ごとに過去の出来事に対する「認識のずれ」が大きな問題となります。たとえば、本人は贈与だと思っていても、他の相続人は「借金だろう」と認識していたり、逆に「あの援助は当然のこと」と片づけられてしまったりします。
このようなズレを放置して協議を進めると、後に不満が噴出し、協議書の無効や裁判に発展する危険性もあります。だからこそ、各相続人の立場や思いを丁寧に聞き取ったうえで、客観的な資料を用いて話し合いを進めることが大切です。
分割協議書の書き方
遺産分割協議書は、協議の結果を明文化し、法的証拠とする重要な文書です。形式は自由ですが、一般的には相続人全員の署名・押印が必要で、財産の内容と分割方法が明確に記載されていることが求められます。
特別受益がある場合は、その内容をどこまで記載するかがポイントになります。記載することで後のトラブルを防ぐ効果もありますが、場合によっては別紙にまとめたり、協議書に盛り込まず内部資料として保存することもあります。
西嶋洋行政書士事務所では、それぞれの家庭の事情に応じて、最適な文書構成をご提案しております。
調停・審判に移行する場合
協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むことになります。これは法的手続きであり、裁判所が関与して相続人間の意見調整や判断を行います。
特別受益に関しても、この段階で改めて主張・立証を求められるため、証拠や説明資料の準備が必要不可欠です。特に、第三者の証言や振込記録などが求められることもあります。
調停や審判は精神的・時間的負担が大きいため、できる限り協議の段階で解決するのが理想です。
西嶋洋行政書士事務所のサポート
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡を中心に、遺産分割協議を円満かつスムーズに進めるための支援を行っています。
具体的には、まず相続関係説明図や財産目録を作成し、相続人全員の関係性と財産の全体像を可視化します。そのうえで、特別受益に関する情報を収集・整理し、どのように持戻しを行うべきかを法的に検討します。
さらに、相続人一人ひとりの事情や意見を踏まえた分割案を提案し、必要に応じて協議書の作成、署名押印の取得、登記や税務手続きの専門家との連携まで、ワンストップで対応可能です。
「親族で揉めたくない」「でも、納得できる形で相続を終えたい」そんなお悩みをお持ちの方に対して、地元に根ざした信頼と、法律的な知識の両面から支えるサービスを提供しています。
特別受益が関係する遺産分割にお悩みの方は、ぜひ西嶋洋行政書士事務所までお気軽にご相談ください。感情のもつれを最小限にしながら、理性的な解決を一緒に目指してまいります。
特別受益の予防と対策

生前贈与とその記録
特別受益による相続トラブルを未然に防ぐために最も効果的なのが、生前贈与の記録を正確に残しておくことです。多くのケースでは、贈与があったことは覚えていても、その内容や金額、時期、意図などが曖昧なために争いが起こります。
たとえば、長男に住宅資金を援助した場合、その金額や目的、贈与か貸付かといった取り扱いを明確にしておけば、他の相続人が「これは特別受益ではないか」と主張した際にも冷静に説明することができます。
贈与契約書の作成や、通帳へのメモ、家族間での覚書など、小さな記録でも後の証拠として有効です。また、不動産や大きな金額の贈与については、贈与税の申告と納付をしておくことで「正式な贈与」であったことが証明されやすくなります。
西嶋洋行政書士事務所では、こうした生前贈与の内容を記録・整理するための書類作成支援や、贈与契約書の作成にも対応しております。相続発生後のトラブルを予防するためには、相続が始まる前からの準備が何より重要です。
家族会議の重要性
特別受益に対する認識を家族間で共有しておくことは、トラブル防止に非常に効果的です。贈与を受けた側と、それを見ていた兄弟姉妹で認識にズレがあると、将来的に「そんな話は聞いていない」という事態を招きます。
そのため、親が生前に家族全体で話し合いの場を持ち、「これは援助として渡すが、相続時には持戻しするつもりだ」などと明確に意思表示することが、円満な相続への第一歩です。
西嶋洋行政書士事務所では、家族会議を円滑に進めるための進行支援や事前相談も承っております。
遺言書による対処
特別受益が争いにならないようにするもう一つの方法が、遺言書の作成です。遺言書の中で、「〇〇に贈与した住宅資金は、相続分とは別とし、持戻しを免除する」といった内容を明記することで、法的に明確な意思を残すことができます。
また、逆に「贈与分を持戻して計算するように」と明示すれば、相続人間での認識の統一にもつながります。
西嶋洋行政書士事務所では、実際の贈与内容や家族関係をヒアリングした上で、最も効果的な遺言書の内容をご提案しております。
第三者の介入による透明性確保
相続や贈与の話は、家族間だけで進めると不透明になりやすく、後に不信感が残る原因となります。だからこそ、第三者である行政書士などの専門家が関与することで、手続きの透明性と公平性を担保することが可能です。
専門家が贈与契約書を作成したり、話し合いの記録を残すことで、「きちんと手続きがされていた」という信頼性が確保されます。特に兄弟姉妹間で温度差がある場合は、専門家を交えた場の方が納得感も生まれやすいです。
山形県最上郡での相続対策
山形県最上郡では、農地や山林、不動産などが相続財産に含まれるケースが多く、現金化が難しい遺産の分割が課題になることが多いです。こうした状況の中で、長男が不動産を引き継ぎ、他の兄弟姉妹には金銭で調整するという慣例も見受けられます。
しかし、このような分割は一歩間違えると「特別受益」として扱われ、不公平感からトラブルに発展するリスクがあります。
西嶋洋行政書士事務所では、最上郡の相続事情に精通しており、地元の不動産事情や家族構成に合わせた具体的なアドバイスが可能です。また、農地の相続や農業委員会への届け出手続きなど、地域特有の相続問題にも対応しています。
さらに、将来の相続トラブルを防ぐための生前対策や遺言書作成、贈与契約書の整備などを一貫してサポートしております。「うちは家族仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続時には予想外の摩擦が生じるものです。だからこそ、今からできる備えが重要です。
相続において「特別受益」が問題になる前に、専門家と一緒に対策を講じることが、家族全体の安心と信頼につながります。
Q&A:よくあるご質問にお答えします

Q1:特別受益って必ず遺産分割に反映されますか?
いいえ、相続人全員が持戻しを行わないことに合意すれば、特別受益を反映しない分割も可能です。また、被相続人が遺言で「持戻し免除の意思表示」をしている場合にも、特別受益として考慮されないケースがあります。
Q2:どこまでの援助が特別受益になりますか?
結婚費用、住宅取得費、学費など高額な援助が対象になることが多いです。一方で、日常生活費や一般的な小遣いなどは特別受益には含まれません。ただし、判断基準は個別事情によるため、専門家の判断が必要です。
Q3:口頭での援助も特別受益になりますか?
はい、書面がなくても実際に金銭や物品を受け取っていれば特別受益と認定される可能性があります。ただし、証拠が不十分な場合は主張が認められないこともあるため、証拠の確保が重要です。
Q4:特別受益を証明するには何が必要ですか?
通帳の振込履歴、贈与契約書、メモ、メール、家族の証言などが証拠になります。立証責任は、特別受益があったと主張する側にあるため、資料の準備は念入りに行いましょう。
Q5:相続人の1人が特別受益を否定した場合どうなりますか?
合意が得られなければ遺産分割協議は成立せず、家庭裁判所での調停・審判に進むことになります。その際には、裁判所が証拠に基づいて判断を下します。
Q6:遺言で特別受益を免除できるって本当ですか?
はい、被相続人の遺言で「持戻し免除の意思表示」があれば、特別受益の扱いを変更できます。ただし、内容が曖昧だと争いのもとになるため、専門家の関与が望ましいです。
Q7:西嶋洋行政書士事務所ではどんなサポートが受けられますか?
特別受益に関する事前相談、遺産分割協議書の作成、証拠整理、家族間の調整支援、遺言書作成など、相続に関する一連のサポートを提供しています。山形県最上郡の実情を理解した対応が強みです。
まとめ

特別受益とは、ある相続人が生前に特別な援助を受けていた場合に、その分を遺産から差し引いて調整する仕組みであり、遺産分割における公平性を保つうえで重要な考え方です。しかし、その判断基準や持戻しの有無、評価額の算定方法などは非常に複雑で、相続人間での誤解やトラブルを生みやすい分野でもあります。
生前贈与の記録や遺言による意思表示、家族会議の実施などを通じて、相続発生後の争いを未然に防ぐことが可能です。また、争いが生じた場合には、証拠の提示や話し合いの調整など、専門的な知識と中立的な立場を持った第三者の関与が重要です。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡という地域の家族事情や相続慣習を熟知したうえで、法律的・感情的な面の双方に配慮した相続サポートを行っております。特別受益に関するお悩みがある方、遺産分割を円滑に進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
「あのとき相談してよかった」と思っていただけるよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。
-
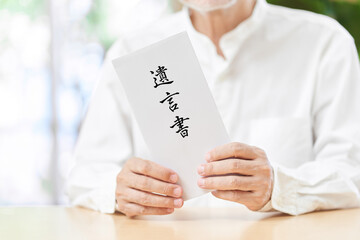
遺言書における付言事項の重要性と記載方法 – 山…
遺言書は、相続人に対して財産をどのように分配するかを明確に伝えるだけのものと捉えられがちです。しかし、実際には遺言書は単なる財産分配の指示書ではなく、遺族に故人の想いや感謝の気持ちを伝えるための重要な手段としても役立ちま…
-

遺言書が後から出てきたら?山形県最上郡の西嶋洋行政書士事務所…
遺産相続の手続きが一段落し、ようやく家族間の話し合いや手続きが落ち着いたと思った矢先、「遺言書が後から出てきた」という状況に直面することは決して珍しいことではありません。このような場合、すでに終わったと考えていた遺産分割…
-
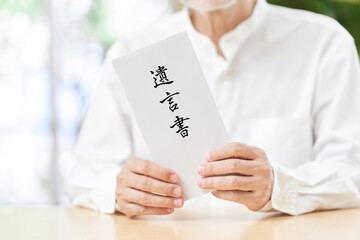
西嶋洋行政書士事務所が教える!遺言書代筆のポイントと注意点
遺言書は、自分の意思を法的に明確に示すための非常に重要な文書です。人生の最後における大切な意思決定を記録し、遺族や関係者に対してその意思を確実に伝えるための手段として、多くの方が遺言書を作成することを検討します。しかし、…
アクセス
ACCESS

- 住所
- 〒999-6401
山形県最上郡戸沢村大字古口341番地1
JR陸羽西線「古口駅」より徒歩3分
- Tel
- 090-1931-6382
- FAX
- 0233-72-2662
- 営業時間
- 9:00~12:30
14:00~17:30
- 定休日
- 土日祝日