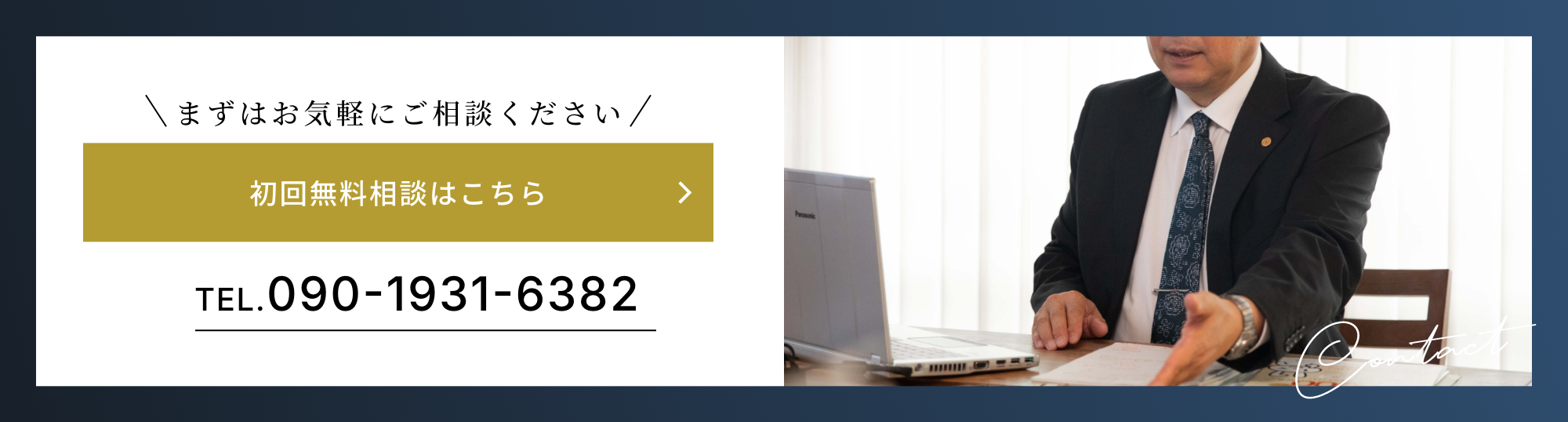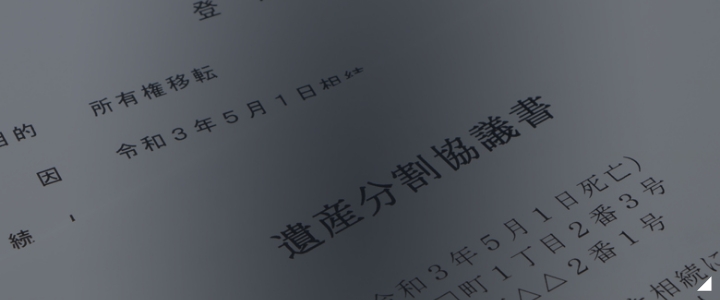ブログ
遺産分割割合は自由に決定できる?|山形・最上郡の行政書士が解説

このページにたどり着いた方の多くは、「相続において自由に割合を決めることができるのか?」という疑問をお持ちではないでしょうか。実際、相続における分割割合は法律上定められた法定相続分が基本となりますが、実はそれだけにとどまりません。相続人全員の合意があれば、遺産分割の割合は自由に決めることが可能です。
しかしながら、現実には「自由」とは言っても多くの落とし穴や注意点が存在します。法律的な枠組みや相続人間の関係性、税務上の扱い、不動産や預貯金の名義変更の手続きなど、専門的な知識が必要になる場面も多く見受けられます。
本記事では、山形県最上郡にて行政書士事務所を運営する西嶋洋行政書士事務所が、遺産分割における割合の自由について、わかりやすくかつ専門的に解説いたします。最終的には、「なるほど、納得できた」と思っていただき、そして「西嶋洋行政書士事務所に相談してみたい」と思っていただけるような内容を目指しております。
相続に関して悩まれている方や、これから遺産分割の話し合いを控えているご家族の皆様にとって、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。
遺産分割割合の自由とは

相続が発生した際、多くの方が「法定相続分どおりに遺産を分けなければならない」と思われがちですが、実際には相続人全員の合意があれば、分割の割合は自由に決定できます。これは「遺産分割割合の自由」と呼ばれ、法律で明確に認められた考え方です。
遺産には、現金や預金、不動産、株式、自動車、日用品など多岐にわたる財産が含まれます。これらを分ける際、単純に法定相続分で均等に割ることが必ずしも公平とは限りません。生前に特定の相続人が親の介護をしていた場合や、事業承継のために資産を一括で受け継ぐ必要がある場合など、個別事情に応じた柔軟な分割が望まれるのです。
遺産分割の割合を自由に設定できるということは、相続人間の話し合いの結果を最優先できるという意味でもあり、家族間の納得感を大切にした分割が可能になります。ただし、この自由には前提条件と注意点があります。それについては次の項目で詳しく解説いたします。
法定相続分との違い
日本の民法では、相続が発生した際に適用される「法定相続分」が定められています。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、配偶者は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつが目安とされます。
しかしこれは、あくまで「協議が成立しない場合の目安」であり、絶対的なルールではありません。相続人全員が納得すれば、たとえば長男がすべて相続し、次男や三男は相続を放棄するという形でも成立します。
このような取り決めをするには、遺産分割協議という話し合いが不可欠です。そこで大切になるのが、全員一致での合意です。一人でも同意しない相続人がいれば、自由な割合の分割はできません。そのため、法定相続分との違いを正しく理解したうえで、合意形成のプロセスを丁寧に進める必要があります。
相続人間の話し合いが前提
遺産分割割合の自由は、相続人全員の合意があって初めて成立します。これは法律上の大原則であり、どれだけ合理的な提案であっても、ひとりでも反対する相続人がいれば、その分割内容は成立しません。
たとえば、「長男が親の介護を長年担ってきたから、遺産の大半を長男に」といった提案も、他の相続人の同意がなければ認められないのです。つまり、合意形成のプロセスそのものが非常に重要となります。
この話し合いは、被相続人が亡くなった後に始まりますが、感情的な対立が生じやすく、過去の家族関係が影響を及ぼすこともあります。冷静に、そして公平に協議を進めるためには、中立的な専門家の関与が大変有効です。西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡の地域性や家族事情を踏まえたサポートを行っており、スムーズな話し合いの実現をお手伝いしています。
民法における柔軟な運用
日本の民法では、法定相続分はあくまで「目安」であると定められています。相続人が合意すれば、その目安に従う義務はないという点が非常に重要です。
この法制度の背景には、「遺産は家族のものであり、家族の判断で自由に分けてよい」という考え方があります。そのため、家庭ごとの事情に応じた柔軟な分割を可能とすることで、実情に即した相続が可能になるのです。
ただし、自由に分割できるとはいえ、税務や登記といった法律の枠組みに則った対応が求められます。協議内容が無効になったり、相続税に想定外の課税がされるケースもあるため、必ず法律の専門家と連携して進めることが推奨されます。
不動産や預貯金の分け方
遺産分割の対象にはさまざまな財産が含まれますが、とくに問題になりやすいのが不動産と預貯金の分け方です。
預貯金は、口座単位で金額が明確であるため、比較的分けやすい財産といえます。相続人がそれぞれの希望額を明示しやすく、協議も進みやすい傾向があります。
一方、不動産は分割そのものが困難なケースが多く見られます。たとえば自宅を共有名義にするのか、売却して金銭で分けるのか、誰か一人が相続して他の相続人に代償金を支払うのか、複雑な判断が求められる場面が多いのです。
こうした財産ごとの特性を正しく理解し、納得のいく分割案を練ることが、相続トラブルを回避する鍵となります。
山形県最上郡における事例
山形県最上郡は、家族同士のつながりが強く、土地に根差した生活を送っている方が多い地域です。そのため、相続の際にも「実家の土地をどうするか」「跡取りに集中して相続させたい」といった要望が多く見られます。
たとえば、ある家では農地を含む広大な土地を一人の相続人が引き継ぎ、他の相続人には預金や保険金で調整するというケースがありました。このような分割割合の自由な取り決めは、地元に根ざした視点を持つ専門家のサポートによって、円満に進められることが多いのです。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡の地域性を熟知しており、地元ならではの相続事情やご家庭の背景を丁寧にヒアリングしたうえで、柔軟かつ納得のいく遺産分割をご提案しています。
遺産分割協議書の重要性

遺産分割割合を自由に決定した場合、その内容を正式に記録し、証拠として残すために必要なのが「遺産分割協議書」です。この書類は、相続人全員が合意した遺産の分け方を明文化するものであり、今後の相続手続きや税務申告、不動産登記などに不可欠となります。
遺産分割協議書がなければ、多くの相続手続きが進められません。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しを行う際、金融機関や法務局から必ず提出を求められます。また、将来、相続人間で「言った言わない」の争いを避けるためにも、協議内容を文書に残すことが大切です。
山形県最上郡においても、相続に伴う不動産登記や口座解約において、協議書の内容が不十分だったために手続きが遅れるケースが多く見受けられます。そこで重要になるのが、正確かつ法的に有効な協議書の作成です。
西嶋洋行政書士事務所では、遺産分割割合の自由を尊重しつつ、正確な協議書を作成する支援を行っています。地域事情に精通した専門家が、相続人間の意思を明確に反映した文書を丁寧に仕上げますので、初めての方でも安心です。
法的効力と必要性
遺産分割協議書は、ただの「覚書」や「メモ」ではなく、法的に効力を持つ正式な書類です。相続人全員の署名押印が揃っていれば、法的な証明として利用でき、各種相続手続きに使用されます。
協議書に基づいて不動産の名義変更を行う場合、法務局はその内容を重視して登記を進めます。つまり、協議書に記載された割合や相続方法が、実際の登記内容となるのです。また、税務署もこの協議書をもとに相続税の課税対象を判断することがあります。
このように、遺産分割割合の自由を実現するには、協議書の内容が正確であることが非常に重要です。専門知識が求められるため、行政書士などの専門家に依頼することが推奨されます。
不備によるトラブルの事例
遺産分割協議書に不備があると、相続手続きがストップしてしまうことがあります。よくあるトラブルとしては、記載内容に漏れがあったり、署名・押印が揃っていなかったり、法定相続人以外の名前が含まれているケースです。
例えば、山形県最上郡のあるご家庭では、長男が主導して協議書を作成したものの、次男が内容に納得していなかったことから署名を拒否し、不動産の名義変更が長期間できなかった事例がありました。こうした事態は、相続人間の信頼関係を悪化させる原因にもなります。
また、税務署から否認されるような曖昧な表現や、記載日と実際の協議日が一致していない協議書は、後々の税務調査で問題になる可能性もあります。小さなミスが大きなトラブルに発展するのが相続の怖いところです。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、遺産分割割合の自由を正確に反映した、適法な協議書の作成が欠かせません。
自筆と専門家作成の違い
遺産分割協議書は自筆でも作成可能ですが、法律的に有効な形式で作られていないと意味をなさないことがあります。
例えば、誰がどの財産を取得するかが不明確だったり、「子どもたちで仲良く分けることとする」といった曖昧な表現では、金融機関も法務局も受け付けてくれません。法的要件を満たしていない協議書は、無効とみなされる可能性があるのです。
一方で、行政書士などの専門家が作成した協議書は、法的根拠に基づき、相続人全員の意思が明確に記された内容で、あらゆる手続きに対応できる信頼性を持っています。また、万が一、将来トラブルが生じた際にも、強い証拠力を持つ文書となります。
遺産分割割合の自由を活かすには、その内容を正確かつ法的に有効な形で表現することが不可欠であり、その点で専門家の関与は大きな意味を持ちます。
登記や税務との関係
遺産分割協議書の内容は、不動産の登記変更や相続税の計算にも密接に関わります。たとえば、協議書に明記されていない相続人名義で不動産登記を行うことはできません。
また、税務署に提出する相続税の申告書においても、誰がどの財産を取得したかが明確になっていなければ、課税額の計算ができず、申告そのものが認められなくなる場合があります。
遺産分割割合の自由が認められていても、それを証明する手段がないと、公的機関では受け付けてもらえないという厳しい現実があるのです。
さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税務上の特典を受けるには、協議書の内容と整合性のある申告が求められます。適当に作成した協議書では、こうした特例の恩恵を受けることもできません。
西嶋洋行政書士事務所のサポート
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡で多くの相続案件に対応してきた実績と経験をもとに、正確かつ迅速な遺産分割協議書の作成を行っています。
相談者様のご事情やご家族の構成、遺産の内容を丁寧にヒアリングした上で、遺産分割割合の自由を最大限に活かしたご提案をさせていただきます。
「相続の話し合いがまとまったけれど、どう書類にすればよいか分からない」「不動産や預貯金の手続きで困っている」といったお悩みをお持ちの方には、具体的な手続きの流れや書類の準備まで、一貫してサポートしております。
特に山形県最上郡にお住まいの方にとって、地元で信頼できる専門家に相談できることは、大きな安心材料となるはずです。お気軽に西嶋洋行政書士事務所までご相談ください。
遺産分割割合の自由が生む課題

遺産分割割合の自由という制度は、柔軟で実情に即した遺産の分け方ができる反面、思わぬ課題やトラブルを引き起こすこともあります。特に、相続人間で価値観や考え方が異なる場合には、分割の話し合いが難航しやすくなります。
遺産の分け方には明確な正解がないため、「公平」と感じる基準が人それぞれ異なるのです。たとえば、「介護をしたのだから多くもらって当然」と考える人と、「相続は平等であるべきだ」と考える人の間には、基本的な価値観のギャップが存在します。
また、法定相続分から大きく逸脱する内容で分割を進めようとすると、遺留分の侵害や他の相続人の反発といった法的・感情的な問題も発生しやすくなります。
この章では、遺産分割割合の自由が引き起こしうるさまざまな課題について詳しく解説し、それらにどう向き合い、どう乗り越えていくべきかを明らかにします。
感情的な対立の発生
遺産分割において、最も深刻な障害となるのが「感情的な対立」です。相続という場面では、幼少期の家族関係や過去のわだかまりが一気に表面化することがあります。
「兄ばかりが優遇されてきた」「介護は私がしたのに何も報われない」といった不満が、協議の場で爆発することも少なくありません。
このような状況になると、本来は財産の分け方を話し合う場であったはずの協議が、過去の感情のぶつけ合いになってしまい、建設的な対話ができなくなってしまいます。
山形県最上郡でも、兄弟間で長年の不信感が募っていたケースでは、わずかな金額の差でも納得できないと主張し、遺産分割が数年にわたり停滞した事例がありました。これは決して珍しいことではありません。
冷静で公平な第三者の立ち会いがあることで、当事者同士の対立を和らげ、話し合いを建設的に導くことが可能になります。
一部相続人の不同意問題
遺産分割割合を自由に設定するには、相続人全員の同意が不可欠です。これは法律で定められた絶対条件であり、一人でも同意しなければ協議は成立しません。
「兄と弟は合意しているが、妹が納得していない」という状況では、協議書の作成も、登記・手続きも一切進めることができません。
最上郡での事例では、相続人の一人が遠方に住んでいて連絡が取れず、何カ月も手続きが進まないというケースも見られました。このような場合、意図的に遅らせていると判断されれば調停や審判に進むことになります。
西嶋洋行政書士事務所では、音信不通の相続人への通知、意思確認の段取りなども丁寧に対応し、協議成立に向けた環境づくりを行っています。
認知症や未成年者の関与
相続人の中に認知症の高齢者や未成年者がいる場合、その人の意思確認や法的同意の取得が困難になります。
認知症の方が判断能力を失っている場合には、家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人を選任してもらわなければなりません。未成年者が相続人となっている場合も、法定代理人の関与が必要となります。
こうしたケースでは、通常よりも手続きが長期化・複雑化しますが、法的に正当な手続きを経ることで、後の無効リスクを防ぐことができます。
西嶋洋行政書士事務所では、成年後見制度や特別代理人の選任手続きも含めて、ワンストップで対応可能です。
公平性の捉え方の違い
「公平」とは何か――これは相続における最も難しいテーマの一つです。相続人一人ひとりが異なる価値観を持っており、全員が「自分が正しい」と感じていることが多いのです。
例えば、「長男が親と同居していたから多くもらうのが当然」という考えと、「全員平等であるべき」という考えは、どちらも間違いではなく、ただ立場が違うだけです。
しかし、この違いを無視して無理に話を進めようとすると、不満や不信感を生み、将来的な人間関係に深刻なひずみを残すことになりかねません。
西嶋洋行政書士事務所では、全員の声に耳を傾け、納得感のある分割案を引き出す調整役としての役割も果たしております。
トラブル予防のための助言
遺産分割割合の自由を活かすには、予防的な視点が非常に重要です。つまり、問題が起きる前に、起こりそうな問題を想定しておくということです。
相続が発生する前に、被相続人が生前に意思表示をしておく、家族間であらかじめ方向性を確認しておく、専門家を交えて定期的に見直しをするなどの対策が非常に有効です。
また、実際に相続が発生した後は、早期に行政書士などの専門家に相談し、冷静かつ的確なアドバイスを得ることが大切です。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡での地域事情や家族構成に応じた、オーダーメイドの相続支援を行っております。相続トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
相続人全員の合意を得る方法

遺産分割割合の自由を実現するためには、相続人全員の同意が絶対条件となります。法律上、一人でも異議を唱える相続人がいれば、遺産分割協議は成立しません。そのため、話し合いをどのように進めるか、そして合意形成をどのように達成するかが、非常に重要なポイントとなります。
しかし、現実には相続人同士の考え方や感情がぶつかり合い、合意が得られないケースも多々あります。だからこそ、冷静な対応と戦略的な進め方が求められるのです。
この章では、相続人全員の合意を得るための具体的な方法、心構え、そして調整における専門家の役割について解説します。山形県最上郡の地域性に根差した対応ができる西嶋洋行政書士事務所だからこそできる調整支援についても、詳しくお伝えします。
協議を円滑に進めるポイント
協議をスムーズに進めるためには、事前準備と段取りが非常に重要です。いきなり話し合いの場を設けるのではなく、あらかじめ各相続人の希望や立場を把握しておくことで、無用な衝突を防ぐことができます。
また、会議の場では「感情論ではなく、事実に基づいて冷静に話し合う」というルールを共有しておくと、感情的な衝突を防ぐ効果が期待できます。
さらに、特定の相続人が主導して協議を進める場合には、他の相続人が不信感を抱かないように配慮することが大切です。誰もが納得できるよう、進行役として中立的な立場の第三者が入ることが理想的です。
コミュニケーションの工夫
相続人が複数人いる場合、全員のスケジュールや考えをすり合わせるのは容易ではありません。特に、遠方に住む相続人や、普段あまり連絡を取っていない親族がいる場合は、コミュニケーションの工夫が必要です。
電話やメールだけでなく、オンライン会議やLINEグループなど、現代のツールを活用することで、連絡や共有の効率を高めることができます。
また、誤解を避けるためには、話し合った内容を必ず文書でまとめておくことが有効です。記録を残すことにより、後々の「言った・言わない」トラブルを防止できます。
西嶋洋行政書士事務所では、文書化のアドバイスや資料作成の代行も行っており、安心して協議を進められる環境づくりを支援しています。
中立的な専門家の活用
遺産分割割合の自由を話し合う場では、相続人それぞれが利害関係を持っているため、どうしても偏りや対立が生じがちです。このような時に力を発揮するのが、第三者である専門家の存在です。
行政書士のような中立的立場の専門家が入ることで、相続人全員にとって公平な意見交換が可能になります。また、法律や税務、手続きに関する正しい情報を提供することで、納得感を得やすくなります。
特に、協議の初期段階から関与することで、将来的なトラブルの芽を早期に摘み取り、無駄な対立を避けることができます。
合意形成の手続き
合意形成には、協議→文書化→署名・押印というステップが必要です。形式としては、口頭の合意では不十分であり、必ず「遺産分割協議書」という形で残す必要があります。
この協議書には、誰がどの財産をどのように相続するかを明記し、相続人全員が署名・押印を行うことが求められます。印鑑証明書の添付も必要となるため、準備には一定の時間と手間がかかります。
一方で、この手続きを正しく踏むことで、その後の名義変更や税務手続きがスムーズに進むようになります。
西嶋洋行政書士事務所では、この一連の手続きを丁寧にサポートし、初めての方でも安心して進められるようお手伝いしています。
西嶋洋行政書士事務所の調整力
山形県最上郡に根ざして活動する西嶋洋行政書士事務所では、相続人間の調整役として、多くの実績と信頼を築いてきました。
単なる書類作成にとどまらず、家族間の気持ちの橋渡し役として、円満な協議の実現をサポートしています。地元ならではの風習や人間関係に配慮した対応ができるのも、当事務所の大きな強みです。
「話し合いの場をどう作ればいいかわからない」「親族が対立していて困っている」といったお悩みがある方は、ぜひ一度、西嶋洋行政書士事務所にご相談ください。
遺産分割の自由とその限界

遺産分割割合の自由は、相続人全員の合意によって柔軟に遺産を分けることができる非常に便利な制度ですが、その自由には必ず「限界」や「制約」も存在します。
一見、どんな分け方でも可能に思える遺産分割ですが、法律の枠組みを超えた取り決めや、他の権利者の権利を侵害するような分割方法は認められません。特に注意すべきなのは、相続税や贈与税との関係、遺留分の侵害、家族信託制度との誤解、そして将来的な争いの芽です。
この章では、遺産分割割合の自由が及ぶ範囲と、超えてはならない法的・実務的な限界について詳しく解説いたします。山形県最上郡での事例も交えながら、西嶋洋行政書士事務所が実際にどのような支援を行っているのかもご紹介いたします。
相続税・贈与税との関係
遺産分割割合の自由は、あくまで相続人間の協議において自由に決めてよいという話であり、税務上の取り扱いとは別問題です。
たとえば、本来相続人でない人に遺産を分け与えた場合、それは「贈与」とみなされることがあります。また、協議の内容によっては、相続税の負担が不公平になり、税務署から調査対象とされるケースもあります。
さらに、相続人同士の間で一方的に多額の財産を取得した場合、「みなし贈与」として贈与税の課税対象になる可能性もあるため注意が必要です。
西嶋洋行政書士事務所では、相続税専門の税理士と連携し、税務的な観点からもリスクのない遺産分割をご提案しています。
遺留分の主張について
遺産分割割合の自由は、相続人の合意が前提ですが、合意できなかった場合には「遺留分」という最低限の取り分を法律で保護されている相続人が主張できる制度があります。
例えば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人(次男・長女など)は法定の遺留分を侵害されたとして、請求することが可能です。
このように、自由な分割がすべての相続人に受け入れられない場合には、法律が一定のセーフティネットを設けているのです。
最上郡でも、過去に遺留分侵害請求によって協議が白紙に戻った事例がありました。事前に相続人の立場と法的権利を明確に把握することが、不要な争いを避ける第一歩です。
家族信託との違い
最近では、遺産分割の代わりに「家族信託」を利用する方も増えています。しかし、家族信託と遺産分割は性質や目的がまったく異なる制度です。
家族信託は、生前に財産管理を信託契約によって他者に任せる制度であり、相続後の財産分割ではなく、認知症対策や事業承継に活用されることが多いのが特徴です。
一方、遺産分割は被相続人の死亡後に開始される手続きであり、相続人間での合意によって財産を分け合うことが基本です。両者を混同すると、本来想定していた相続対策が機能しない可能性もあります。
西嶋洋行政書士事務所では、家族信託を検討している方に対しても、信託と相続の違いを丁寧に説明し、正しい判断へと導くお手伝いをしています。
将来的な紛争防止策
遺産分割割合の自由を行使した後、時間が経ってから問題が表面化することもあります。たとえば、「当時は合意したが、今になって不満が出てきた」「協議書をなくしてしまった」というケースでは、再び相続人間の関係が悪化することも珍しくありません。
このような将来的なトラブルを防ぐためには、協議内容をできる限り詳細に文書化し、関係者全員がコピーを保管することが大切です。
また、協議に至った経緯や理由も記録しておくことで、後から「なぜそうなったのか」を客観的に説明できる材料になります。
西嶋洋行政書士事務所では、書類の保管方法や記録の仕方についても具体的なアドバイスを行っており、将来にわたる安心をサポートいたします。
山形県最上郡での実務的アドバイス
山形県最上郡では、代々続く農地や山林を相続するケースが多く、現金や不動産に比べて評価が難しい財産が多く存在します。こうした遺産は、相続人間で価値の捉え方に差が出やすく、遺産分割割合の自由を活用するには慎重な判断が求められます。
また、地域特有の家督制度や跡継ぎ文化も色濃く残っており、「長男に集中して相続させたい」というご相談も多く寄せられています。そのような場合でも、他の相続人が納得できる補償や配慮を同時に検討することが大切です。
西嶋洋行政書士事務所では、地域に根ざした実情を理解したうえで、現実的かつ法的に適正な遺産分割案をご提案しています。相続に不慣れな方にも丁寧にご説明し、安心して任せていただける環境を整えております。
Q&A:よくあるご質問にお答えします

Q1:法定相続分以外で分けても大丈夫ですか?
はい、相続人全員の合意があれば可能です。法律では法定相続分が基準とされていますが、それは「協議が整わない場合」の目安にすぎません。実際には、自由な割合で分割することが認められています。
Q2:一部の相続人が納得しないとどうなりますか?
相続人全員の合意がない限り、遺産分割は成立しません。一人でも反対すれば、家庭裁判所での調停や審判に進む必要があります。できる限り話し合いで解決することが望まれます。
Q3:遺産分割協議書は自分で作れますか?
理論上は可能ですが、法律的に不備のない内容で作成するのは難しいのが実情です。特に不動産の名義変更や相続税申告を伴う場合は、専門家による正確な作成が必要です。
Q4:遺産分割の話し合いはいつ始めればいいですか?
相続開始後(被相続人の死亡後)に行うのが原則ですが、相続トラブルを防ぐために生前から話し合っておくことも非常に有効です。生前対策として遺言書や家族信託を検討する方も増えています。
Q5:遺産を一部の相続人に集中させることはできますか?
可能です。ただし他の相続人が納得する補償や代償金の取り決めが必要です。不公平と感じさせないよう、丁寧な説明と合意形成が不可欠です。
Q6:どのような財産が分割対象になりますか?
預貯金、不動産、有価証券、車、貴金属、生命保険金、さらには借金なども含まれます。財産の種類ごとに分割方法や手続きが異なるため、個別に検討する必要があります。
Q7:西嶋洋行政書士事務所ではどこまでサポートしてもらえますか?
遺産分割協議書の作成はもちろん、相続人間の調整、相続関係説明図の作成、不動産登記の手配、税理士との連携による税務アドバイスなど、相続手続き全般をサポートしております。山形県最上郡を中心に、地域に密着したきめ細かい対応が可能です。
まとめ

この記事では、遺産の分け方を自由に決めることができる制度のメリットと注意点、そしてその具体的な活用方法について、山形県最上郡で実績豊富な西嶋洋行政書士事務所の視点から詳しく解説してまいりました。
遺産分割割合の自由は、相続人全員が納得すれば、法定相続分にとらわれない分け方が可能であるという柔軟性を持つ制度です。しかし、その一方で、全員の合意形成や文書化、税務面での配慮、不公平感の調整など、慎重かつ丁寧な対応が必要とされる複雑なプロセスでもあります。
実際の相続では、感情的な対立や思わぬ法律上の制約が浮き彫りになることも少なくありません。そうした場面こそ、地元の事情に精通し、法律知識と実務経験を持つ専門家のサポートが不可欠です。
西嶋洋行政書士事務所では、山形県最上郡を中心に、相続人一人ひとりの思いを大切にした遺産分割の実現をサポートしております。遺産分割割合の自由を最大限に活かしつつ、法的にも安心できる手続きを進めていきたいとお考えの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
相続は「誰に相談するか」で大きく結果が変わります。西嶋洋行政書士事務所が、皆さまの大切なご家族の未来を守るお手伝いをいたします。
-
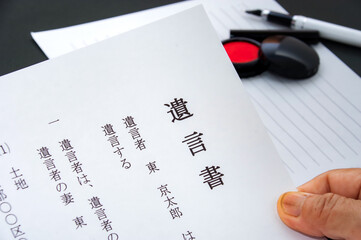
遺言書の有効期限とは?山形県最上郡の西嶋洋行政書士が解説!|…
山形県、特に最上郡にお住まいの皆様へ。「遺言書は一度作成すればずっと有効」と思っていませんか?実はその認識、将来の相続トラブルの原因になるかもしれません。 私たち西嶋洋行政書士事務所には、「昔に書いた遺言書が今でも使える…
-

遺言書が後から出てきたら?山形県最上郡の西嶋洋行政書士事務所…
遺産相続の手続きが一段落し、ようやく家族間の話し合いや手続きが落ち着いたと思った矢先、「遺言書が後から出てきた」という状況に直面することは決して珍しいことではありません。このような場合、すでに終わったと考えていた遺産分割…
-
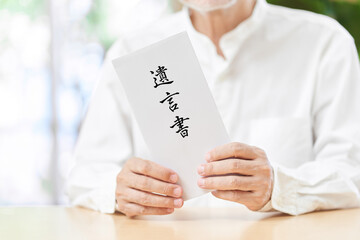
遺言書における付言事項の重要性と記載方法 – 山…
遺言書は、相続人に対して財産をどのように分配するかを明確に伝えるだけのものと捉えられがちです。しかし、実際には遺言書は単なる財産分配の指示書ではなく、遺族に故人の想いや感謝の気持ちを伝えるための重要な手段としても役立ちま…
アクセス
ACCESS

- 住所
- 〒999-6401
山形県最上郡戸沢村大字古口341番地1
JR陸羽西線「古口駅」より徒歩3分
- Tel
- 090-1931-6382
- FAX
- 0233-72-2662
- 営業時間
- 9:00~12:30
14:00~17:30
- 定休日
- 土日祝日